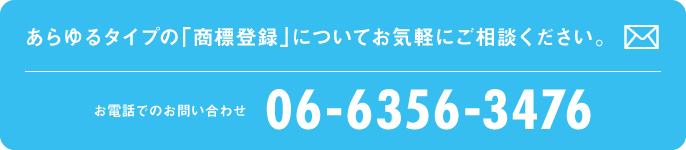![]()
商標関連情報
「三つ葉葵紋」 他人の登録は出所混同(15号)の他、公益事業の権威毀損(6号)等の条項にも反する
異議申立番号 異議2016-900059
確 定 日 平成29年(2017)3月31日
主な関連規程 商標法第4条第1項第15号、同項第6号、同項第19号、同項第7号
事案の概要
水戸徳川家の家紋である「三つ葉葵」が、水戸大神楽の上演等をする者によって、商標登録された。これに対して、水戸徳川家伝来の什宝書籍等の文化財を調査、研究、保存等を目的とし、歴史的資料等の調査研究、徳川ミュージアムの管理運営等を行っている法人が、その取り消しを求めて異議の申立てを行った。
本件商標
指定商品
第21類 「お守り,御札,護符」
第33類 「日本酒」
第41類 「映画・園芸・演劇・又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,大神楽の上演 等
引用使用標章
結 論
本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号、同項第6号、同項第19号及び同項第7号に違反してされたものであるから、その登録を取り消すべきものである。
理由(要旨)
1 家紋及びそれを巡る状況について
家紋は、我が国において家を識別する紋章であり、古くから血筋、また家系等を表す印として用いられてきた。
そして、現代においては、家系を表す印としては、冠婚葬祭において着用される紋付き袴などの和服、墓石、店舗の暖簾、代々続く商家等の家を表す印として一般に利用されている。
このような実情において、家紋からなる商標は、自他商品又は自他役務の識別標識として機能しない。
他方、当該家紋に識別力のある文字等を組み合わせてなる商標等で全体として識別力が認められ、、かつ、当該家紋と類似しない場合、又は、長年企業の商標として使用されるなどによって識別力を有するに至った場合には、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を有するものといえる。
2 申立人について
申立人は、1967(昭和42)年2月に設立された「財団法人水府明徳会」を前身とし、2011(昭和23)年3月に公益財団法人として認可され、同年4月から「公益財団法人徳川ミュージアム」と名称変更したものであって、その目的は、水戸徳川家伝来の什宝書籍等の文化財を調査・保存等をし、文化の向上に寄与することとし、文化財公開、イベント、調査研究、文化財修復、助成事業等を行っている。
3 引用使用標章について
引用使用標章は、水戸徳川家の家紋であって、申立人の前身の財団法人設立時にシンボルマークとして定められ、申立人のホームページ、申立人主催の講演会のチラシ、申立人美術館において販売する印籠、はがき等の商品に使用されている。また、申立人の代表者(理事長)は、水戸徳川家の末裔であり、申立人美術館において、水戸家伝来の品々や文書類を保存・展示公開している。
以上によって、申立人により水戸徳川家伝来の品々や文書類の保存・展示公開等の文化的・経済的価値の維持・管理がされ、その活動とともに引用使用標章は、徳川家等を表示する著名な三つ葉葵紋のうち、水戸徳川家を表示する家紋ないし申立人を表示する標章として、著名なものであって、申立人によって管理されている。
3 商標権者について
商標権者は、伝統芸能を継承するイベントプロダクション、芸能プロダクションである。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
引用使用標章は、水戸徳川家の祖先である徳川光圀・徳川斉昭を祀る常盤神社において、神社幕等に使用されている。神社では、一般にお守りや御礼が取り扱われている。本件商標の指定商品及び役務は、申立人の事業活動に関連するものであるから、その需要者等を共通にする。
本件商標と引用使用標章の類似性の程度、引用使用標章の著名性の程度、商品又は役務の関連性及び需要者等の共通性等を総合勘案すれば、その商品又は役務の出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
5 商標法第4条第1項第6号、同項第19号及び同項第7号該当性について
仮に、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当しないとしても、商標法第4条第1項第6号、同項第19号及び同項第7号のいずれかの号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第6号該当性について
ア 商標法第4条第1項第6号は、国や公益に関する団体・事業等の公益性にかんがみ、その権威を尊重するとともに、出所の混同を防いで需要者の利益を保護しようとする趣旨に出たものであり、これら団体を表示する著名な標章と同一又は類似の商標については、これら団体の権威を損ない、また、出所の混同を生ずるものとみなして、無関係の私人による登録を排除しようとするものである。
申立人及び同人が行う事業は、商標法所定の「公益に関する事業であって営利を目的としないもの」に該当する。また、引用使用標章は、著名であり、本件商標とは、極めて類似する。
イ 商標権者の意見に対して
(ア)商標権者は、「商標権者の代表者が継承した水戸大神楽は、江戸時代に当時の水戸徳川家当主から三つ葉葵紋の使用を許可された御用神楽司から引き継いだ伝統芸能であり、商標権者は、大神楽の上演等について三つ葉葵紋の商標登録を受ける資格がある。」旨主張する。
しかしながら、大神楽の上演について水戸徳川家当主から三つ葉葵紋の使用を許可され使用することと、商標登録を受け独占排他的にに使用することとは、別の問題であり、使用の許可を得ているとしても、商標登録を受ける資格があるとはいえない。
(イ)商標権者は、「大神楽に関する部分だけでも権利を維持したく、指定商品及び指定役務を大神楽に関する部分に限定したい。」旨主張する。
しかしながら、引用使用標章は、申立人を表示する標章として、著名性を獲得しているものであって、本件商標は、それと類似する商標であるから、「大神楽の上演」の役務についても、本件商標の登録を維持することは、団体の権威、信用の尊重や出所の混同を防いで取引者、需要者の利益を保護するという商標法第4条第1項第6号の趣旨からして適切であるとはいえない。
ウ 以上のとおり、本件商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと極めて類似する商標というべきであるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第19号該当性について
ア 引用使用標章は、著名性を獲得しており、本件商標と引用使用標章の構成は、極めて類似する。さらに、商標権者は、申立人と同じ茨城県水戸市に所在する法人であって、三つ葉葵紋に類似する図形について、徐々に引用使用標章に近づけて(注)商標登録を取得したことがうかがえる。
してみれば、商標権者は、引用使用標章が申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして広く認識されていることを承知の上、引用使用標章に化体した顧客吸引力を希釈化させ、その信用、名声を毀損させ若しくはその信用に便乗して不当の利益を得る等の不正の目的のもとに、引用使用標章と極めて類似する本件商標を出願し、登録を受けようとしたものと推認せざるを得ない。
イ 商標権者の意見に対して
商標権者は、「自己の業務に係る商品又は役務に関して三つ葉葵紋の使用を許可され、商標として使用してきた者であるから、不正の目的をもって商標登録出願したものではない。」旨主張する。
しかし、たとえ、商標権者が三つ葉葵紋の使用を許可され、商標として使用してきた者であるとしても、引用使用標章が、水戸徳川家を表示するものとして広く認識されている標章であることを承知していたことは推認できるものであって、不正の目的のもとに、引用使用標章と極めて類似する本件商標を出願し、登録を受けようとしたものというのが相当であるから、不正の目的をもって使用するものといわざるをえない。
ウ 以上のとおり、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内において需要者の間に広く認識されている商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものというべきであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
ア 引用使用標章が、一定の経済的価値を有し、また、その文化的・経済的価値の維持・管理に努力を払ってきた申立人が存在する中で、引用使用標章と何ら関わりのない商標権者が最先の商標登録出願を行った結果、先願者であるということによって、唯一の権利者として独占的に使用できるようになり、申立人を含む他人による利用を排除できる結果となることは、申立人及びその関係者並びにこれを利用する者の利益を害する。商標権者による本件商標の取得は、社会公共の利益に反するとともに、社会の一般道徳観念に反する。
イ 以上のとおり、本件商標の登録は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標というべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
注:本件商標以外の本件商標権者が所有する商標
平成29.6.30発行「審決」より 2017.7.31 ANDO